January 29, 2007
やって来る
●やっぱり「やって来る」らしいっすよ。
●土曜は松岡正剛のイベント「連塾2」にスタッフとして参加。
●とは言っても、事前のグラフィック系作り物なんで、当日はお手伝い的。
●ポスターが思いのほか評判がよくて嬉しかった。田中泯さんも一枚欲しい、と言ってくれたらしい。
●それはおいといて。
●田中泯さんが話の中で、「踊りは内面を出す、というものではなく、身体の外側にあるもんだ、外からやってくるんだ」との土方巽の言葉を引用していた。
●高橋睦郎さんも「詩は向こう側にあるんです。向こうからやってくるんです。そのためにこっちは器を用意しておかなきゃいけないし、磨いておかなきゃいけない」と言っていた。
●やっぱりそうなんだなあ。
●いや、前回書いたのはコンテンツがやって来る、ってことで、デザインそのものがやって来るってことじゃないんだけど。
●そもそも、それを分けてしまったのがよくなかったかもな。
●デザインだってそこに表されているモノのコンテンツの一つだし、見る人と内容の関係そのものがデザインであるはずだ。
●まあ、とにかく「器」を、「型」を持っておく、作っておくのが一つ大事なことだと実感したわけです。
●磨いておかなきゃな。
投稿者 mikandesign : 01:56 AM | コメント (0)
January 24, 2007
器としてのデザイン
●コンテンツが先にあって、それを(視覚的に)明らかにする、伝えるのがデザインなのであれば、やはりコンテンツに合わせたデザインをするべきだろうか?
●そうなると、例えばビジネス、ファッション、思想、美術、など色々な分野に合わせて自分のテイストを変えていかなければならない。
●それとも、個人で、あるデザインテイストなりを持っていて、そこに当てはまるようなコンテンツがやってくるものだろうか?
●もしくは内容に関わらず、そのテイストを当てはめることができるだろうか?
●おそらくはそのどちらでもなく、ある何点かの軸は固定し、ある何点かは変えていくというような、個性と流動性を兼ね備えた方法を持っていなければならないのかもしれない。
●その方法こそが「テイスト」なんだろうか?
●なんにせよ、デザインは、デザイナーは「器」だ。
●そこにどんな料理(コンテンツ)が盛られてこようと、器としての形(型)は崩すことなく、その料理に合わせて、美しく機能的に配膳(レイアウト等)されるべきだ。
●要するに「型」なんだな。
●「型」があること、「型」を持つこと自体が方法なんだろう。
●じゃあその「型(器)」は幾つ用意しておく?
●だれが料理を盛る?
●配膳の仕方はどう変える?
●一つ言えるのは、かつて利休や織部が「利休好み」「織部好み」として茶道具なんかを目利きし、デザインのプロデュースしていったように、「器」は「好み」でいいんじゃないか。
●もちろんその「好み」が天下に通じなきゃ意味ないけど。
投稿者 mikandesign : 02:29 AM | コメント (1)
January 11, 2007
イメージ
●結局、対峙するのはイメージなんだよな。
●こちらのイメージと、相手のイメージ。
●それをいかに言葉にして、何かに仮託して、ある程度形にして、いかに相手に伝えられるか、いかに納得させるか。
●どこで折り合いをつけるのか。
●心のうちにぼんやりあるモノを伝えるのは難しいし、色んな手段を講じなければならない。
●だけど、そんなイメージも、どこかで見たり聞いたりしたモノの複合だろう。
●「自分」のイメージも「どこかの何かが色々に絡み合った」イメージでしかないのかもしれない。
●それを再現するのか、表現するのか。
投稿者 mikandesign : 01:09 AM | コメント (0)
January 10, 2007
17歳のための世界と日本の見方
●年末に出版された、松岡正剛の『17歳のための世界と日本の見方』が結構売れているらしく、嬉しい。
●すでに3刷りが決まったらしい。
●装丁やらを担当したけど、これまでにない松岡像を打ち出すってのが、それなりに苦労した。
●内容も女子大生向けの講義録集なので、すごくわかりやすい。やっぱり内容が表面に出る装丁が、意味と表現が実は一緒だという仮説の、一つの現れなんだろうな。
●それなりにライトな作りに還元したつもりではある。
●自分のデザインした本がどのくらい売れているかってのは、正直気になる。
●直接自分の売り上げには関係ないのだけど…。
●その話は、またそのうち。
●本当に面白い本です。
●ここで言う「17歳のために」ってのは、17歳向けというよりは、17歳の時に読んでおけよってことです。
●本当は今の僕らぐらいが読むのが一番面白くは感じる。
●何が面白いのかって、人間の意識の発生から、東洋・西洋の文明や文化が、宗教や物語とともに、どのように発達し、どこで出会い、そして現代にもどんな問題を残しているのか、ということが、さらっと読めるのだ。
●ある種のインデックスとしても非常に有益だと思う。どこからでも事柄に突っ込める。
●興味ある方、買ってみて下さい。
投稿者 mikandesign : 01:30 AM | コメント (3)
January 08, 2007
ジレンマ[dilemma] 其の壱
●エディトリアルデザインで、鶏と卵のような問題があると思う。
●テキストが先かデザインが先か。
●個人的にはテキストを読んで内容を把握してから、その意味なり構造なりをデザインにしたいと思っているのだけれど、特に依頼原稿の多い雑誌なんかではそうはいかない。先割(先に文字数をデザインで決めてしまう)を求められることが多い。
●一件デザイン優先で、デザイナーにとっては良さそうに思えるが、流し込みを印刷所でやってもらう場合も多く、なかには目も当てられないような組み方があがってくる事もある…。
●おまけに先割の文字数以上で原稿が来ることも多々ある…。
●逆に、テキストが既にあり、内容も把握できる場合でも、明らかに誌面に入らない場合もある…。
●それを無理矢理押し込むと、想定していたデザインが崩れてしまう。
●その時点で無理に文字数を減らしてしまうのも、ライターに申し訳ないし…。
●もちろんそこが腕の見せ所なんだけど。
●書かれているテキストとそのデザインって、実は一緒のものであるはずだし、メディアになった時には、読み手にはそこが分かれているとは思われない。
●でも作る過程では、別のモノになってるんだよな。
●一番良いのは、ライターがデザインもし、デザイナーがテキストも書けることか。
●僕には無理そうですが…。いずれ…。
●ともかく、その間をつなぐ編集者って、一番大事な存在だし、一番大変だとは思います。
●要するに編集的なデザインってのが必要なんでしょうね。
投稿者 mikandesign : 10:03 AM | コメント (1)
January 07, 2007
書誌棚-booklog
●MIKAN-DESIGNのサイトもいずれCMS化するかもしれない。
●こういった形でガチガチにフォーマットを決めてしまっている場合は、そのほうが良いだろうな。
●そうなればもっと頻繁に更新できます。
●ところで、以前からbooklog(ブクログ)というサイトがある。結構有名なので、ご存知の方が多いと思います。
●Amazonから情報を引っ張れて、書誌棚を作れます。
●本当は、読んだ本、家にある本の備忘録などとして使うのが普通なのだろうけど、こんな使い方をしてみました。
●mikan-designの本棚
●そうです。僭越ながら、自分の装丁・デザインしたの本のライブラリーです…。
●こういう使い方をすれば、自分のサイトのbookカテゴリをある程度こっちで簡単にカバーできる。
●ただ、デジタル書誌棚としては、Delicious Libraryの方が優れている。
●OSXのソフトウェアだけど、なにがすごいって、iSightなんかのカメラに本のバーコードをかざすだけで、自動でAmazonから情報を取ってきて、登録できるんです!
●ちょっと感動ものでした。
●ただ古書ってどうなるんだろう? やっぱり手入力?
●ブクログにしろ、Delicious Libraryにしろ、本の判型は無視され、すべて同じ大きさってのはちょっと気になる…。
●まあ、この場合は本の画像の方がおまけみたいなもんか。
投稿者 mikandesign : 12:49 PM | コメント (0)
January 05, 2007
箇条書き
●何人かの友人の真似をして、箇条書きで再開してみる。
●会話をしていると、話がぶっ飛ぶことがよくある。自分の頭の中では変な変換があって、何となく話は続いているのだが、発言すると前後の会話と脈絡がない。
●そういったアタマの構造や考え方を文にするとき、この箇条書きが最適じゃないかと思った。書きやすいし、続けられるかもしれない…。
●メモ代わりにも最適。
●箇条書きは文章構成上良くないと、何かで聞いたか読んだことがあったが、どうしてだっただろうか? 誰か知ってる人教えてください。
●まず、この箇条書きの頭にくる記号・約物を何にするか迷った。なるべく黒味が多いほうが目につきやすい。PCの文字コードは種類が少なく、winでもmacでもとなれば、「●」「■」「◆」「▲」「▼」ぐらいだろうか。個人的には蛇の目がいいのだけど、メールを送る際にもよく使う、「●」にしておくことにする。
●もちろん、内容によって記号を変えるのもありだけど、それは気が向いた時に。
●ここまで書いてみて、無味乾燥な気もするけど、とりあえず、少し続けてみます。
●タイトル付けるって難しいですね。
投稿者 mikandesign : 12:28 AM | コメント (0)
July 29, 2006
久々の……更新
実に2年ぶりくらいに、HPの作品を更新しました。
こまめにやるべきだったけど、しかし2年もためるとは、立ち上げたときは自分でも想像つかなかった。
blogも半年に一回の更新になってるし…。
まだまだ拙いものもばかりで、こうやって眺めているとまだまだがんばれるなと思います。
…と書くと、クライアントの方々には失礼ではないかと思ってしまいます。
拙いものを作るなよと。
もちろん、その時その時で一生懸命やっています。
あくまで成長過程の記録ですので、長い眼で見てやってください。
ご覧になった方は、コメント欄に感想などいただけるとありがたいです。
投稿者 mikandesign : 05:30 PM | コメント (180) | トラックバック
December 14, 2005
横須賀功光展&平安の仮名・鎌倉の仮名展
【横須賀功光展「光と鬼」】
恵比寿の東京都写真美術館へ赴いた。照明演出を藤本晴美さんが手がけているのと、図録の構成を松岡さん+勝井さんが手がけているのだから、いちど見ておかなければならない。
会場は、歩くたびに床がギシギシいうのと、少し狭い印象を除けば、斬新な作りで面白かった。全部観たかなと思うと、あ、この作品まだ観てないという、一種の宝探しのような錯覚に陥る。(一応すべて観たはず)漫画なんかで見る八門遁甲の陣のイメージ。
横須賀功光の写真は、意識してみるのは今回が初めて。
コントラストの強い写真が多く、全体的に黒い印象を受けた。それが、黒い什器の白いフレームの中にあるから、余計に白黒の対比が強調される。一番印象に残ったのは、それらの作品の中で最も白い2点だった。
白い空間の中に、黒い女性がぽつんと小さくポーズをとっている。その位置や空間の構成にもよるものだろうが、まるでミクロの人間のようだった。
全体的な印象でいうと、横須賀功光の作品は、撮られている対象が何であったかをはるかに超えているように感じた。
山口小夜子と山海塾(?)の写真も、白塗りの人々がまるで山口小夜子を取り巻く布や何か別のモノであるように見え、とても人間には見えない。マン・レイへのオマージュである作品らも、何を組み合わせて撮ったものかというのはどうでも良いことに思えた。人体を「人間」としてカメラに収めプリントするのではなく、「何か」にしている。これは本当に「何か」であって、なんと言ってよいのかわからない。松岡さんの文章には「間際」とあった。
オブジェクトやサブジェクトを超えることが「表現」なのかもしれない。
【平安の仮名・鎌倉の仮名】
その足で有楽町の出光美術館へ。前の記事にも書いたが、仮名は日本の文字で本質的な役割を担っているかもしれない、と思っているので、これはぜひ観ておかなければと思っていた。
正直、あまり平安と鎌倉の違いというのには興味が無かった。単にかなの変遷というものを少し観ておきたかった。もちろん、貴族から武士へという社会変化は重要な時代背景だと思うが、連綿と流れている時間の中で、むしろその間を見てみたかった。
ただ、やはりざっくりとした印象でもかなり違っていたように思う。
それは、途中の「手習」に関するパネルにあった、「平安の仮名は乱れ書きやすさび書きが優雅で美しいとされていた…。」という内容に結実していると感じた。Kさんのブログにも、図録を引用しつつそのようなことが書いてあった。
平安の仮名、特に和歌を書く仮名というのは個人の感情で書くことが良しとされ、鎌倉になってくると公文書の記録としての役割が大きくなっていく。記録として読みやすいよう、残りやすいように「フォント化」していくこと、要するに「形式化」することが望まれているように思えた。確かに、同じスクロールの中の一字、を比べてみても、似ている文字になっている。展示も様式別に分かれていて、これは、書き手の名前を冠した一種のフォントであるといえるかもしれない。
「私」の文字から「公」の文字へ、という変遷を見た気がした。記録と文字の関係も考えてみると面白い。
ただ、会場にはおばちゃんが多く、彼女たちがひとつの作品に張り付いてなかなか離れないのには辟易した。恐らく頭の中で運筆しているのかもしれないが、気になる作品に限ってそこを動こうとしなかったので、それらはこれから図録でゆっくり眺めることにする。
後日、藤本さんご本人と会食させていただく機会があり、そのとき「床がギシギシ鳴りますね。」と問うたところ、「甘いわね。あれはわざとよ。足音をさせないで暗いところから急に人が出てきたら怖いでしょ」との解説をいただいた。なるほど、てっきり足音がどうにもならなくて、藤本さんはご立腹かと思っていた。
投稿者 mikandesign : 01:58 AM | コメント (0) | トラックバック
June 02, 2005
文字と非文字
写真をコラージュしていて、ふと思った。
写真に撮られた文字を地に引くのだが、これは一体「文字」なのだろうか?
撮影されている以上、「写真」ではあるが、そこに写っているのは確かに「文字」であり、
たいていの人はそれを文字と認識するはずではある。
しかし、こうやって扱っていると、文字のような気がしてこない。
このように、テキストを打ち込むと、確かにこれは文字である。けれど、見ているのはあくまでモニタであり、そこに映し出されているのは、 デジタル信号が変換された点の集合にすぎない。
よく感じるのは、Illustratorで、文字をアウトライン化した瞬間に、それまで「文字」だったものが「画像」に変わった気がする。実際、PC上において、テキストデータとしてそれを扱えなくなることは、「非文字」といえるかもしれない。
ところが写植の場合、文字は撮影される。撮影されて始めて「文字」としての存在があらわれる。要するに、印画紙に焼き付けられたものが写真であるなら、「文字」=「写真」なのである。
活版の場合、活字が組まれ、紙に押し付けられてこその「文字」である。
では、日本の場合、明治に活字が作られる以前は、それは「文字」ではなかったのだろうか。
そんなはずはない。
現在では、書は文字である上に、ピクチャとして扱われる場合が多いが、活字の流通する以前は少なくとも「文字」ではないことがなかったはずだ。
もちろん、読本などで言えば「書かれたもの」ばかりではなく、「刷られたもの」もたくさんあるのだろうが、原本は誰かの手によって書かれたある形を持っている。(まあ、活字やフォントも元々誰かが書いたものには変わりないだろうが)
それが絵草紙なんかと一緒になったものでも「文字」として流通していた。活字に慣れ親しんだ我々が見ると到底文字には見えないのだが。
要するに、活字の誕生が「文字」と「非文字」という観念を作ってしまったと言えるかもしれない。
それはマクルーハンが言った「文字文化は無意識を生み出した」ということと、近しいものがある。というよりは、活字は、「知性と感性を分断した」ことによって、文字自身の存在を揺らがせる境界のようなものを作ってしまった。その境界が「人間の無意識」なのかもしれないが。
投稿者 mikandesign : 03:18 AM | コメント (3) | トラックバック
May 25, 2005
marginal zone
【マージナルゾーン】 marginal zone
凸版印刷・箔押しした画線の縁に生じるくまどり。版と紙の接する画線部分の外側にインキが押し出されるために生じる現象。[-if- informaiton factory用語集より]
これは活版印刷における現象だ。このインキのはみ出しをふまえて、活字はデザインされる。
例えば、Garamondの「P」や「6」に、妙な隙間があるのはそのためで、これはDTPフォントにも引き継がれている。
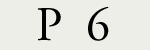
では、写植ではマージナルゾーンは生じないのだろうか。
print-betterというサイトにこうある。
〈写植は、主に平版印刷用(オフセット印刷)に使われるためマージナルゾーンは起きないが、写植機における光学的な露光条件やフィルム製版条件などに影響される。〉
最初に、このマージナルゾーンという活版印刷上の現象を教えてくれたのは、編集者のKさんだった。
Kさんと話しているうちに、ふと思った。
「写植の製版では撮影するのだから、文字の輪郭に多少のぼけが出たり、レンズの拡大率によっては角が削られるはずだ。それは一種のマージナルゾーンではないのだろうか」
あるいは話の中で、Kさんの誘導尋問的にそういう考えに達したのかもしれなかったが、とにかくそれもマージナルゾーンと言えるかもしれない、という結論になった。
いわば、印刷の工程で自発的に曖昧な部分ができてしまうことを、マージナルゾーンが生じると言い換えられるかもしれない、ということだ。
ところが、DTPからの印刷過程ではこれが生じにくい。確かに、オンデマンド印刷などでは少々ぼけ気味に仕上がってくることも多いが、一般的な印刷ではベクトルデータそのままで、仕上がることが望ましい。
特にCTP(computer to plate)などでは、データがそのまま版になるので、マージナルゾーンが生じる隙がない。
そういった「隙」や「曖昧さ」がないからこそ、逆に制作の段階でそれらを作り出そうとする傾向は、最近のデザインではよく見られる。
広告のコピーや、書籍・雑誌のタイトルなどでも、わざと文字の角を丸めて柔らかさを表現したり、コピーを何度もとってノイズを加えたり、手間をかけ、あえてアナログ的な視覚表現にすることで、ある種の「モノ」のしての錯覚を起こさせる。
ex.〈WIRED 日本語版 design:佐藤直樹〉
これは印刷工程上で自発的に起こるのではない。ある意図をもって「マージナルゾーン(≒ノイズ)」を作ろうとしている。決してアナログ回帰ではないだろうが、二進法的デジタル行程のデザインの中で、そのような表現がまた見直されてきているということは、人間の認知・知覚には、ある「曖昧さ」が必要だと言うことかもしれない。
「曖昧さ」は、実は日本文化の特徴のひとつだと思う、という話はまた別の機会に。
投稿者 mikandesign : 05:45 AM | コメント (194) | トラックバック
May 20, 2005
mixed fonts
「混植」と呼ばれる、漢字・かな・英数字をそれぞれ別の書体で組み合わせる技法がある。
例えば、DTPで言えば
漢字:ヒラギノ明朝W3
かな:游築36ポ仮名
英数:Adobe Garamond Reguler
という風に、組み合わせの相性や、サイズを微妙に調整して、組まれたときに美しく見えるようmixされる。
主に「和欧混植」と呼ばれるように、和文と欧文で異なる書体を使うことが多い。
最初、DTP上で「和欧混植」をやっていたときは、和文フォントに含まれている英数文字の書体が美しくないからだろうな、と漠然と考えていた。どう美しいかの基準は別として、確かに欧文書体の、緻密に作られた完璧なプロポーションに比べると、無理矢理に和文書体にテイストをあわせたそれらの書体が、劣って見えるのも仕方ない。ただ、後で知ったことだが、「ジャスティフィケーション」といういわゆる箱組(コラム幅の両端を揃える)をするときに、和欧混植をすると自動ハイフネーション機能(単語間に自動にハイフンがふられ、長い単語でも途中で区切ることができる)が活きてくる、という理由もあるらしい。なんにせよ、個人的には特に新ゴの欧文書体の甘い感じは許せないので、UniversやFrutigerと組み合わせることが多い。
また、以前から「かな」だけのフォントも市販されている。たとえば、味岡がなや、先に挙げた游築36ポ仮名などもそのひとつである。他にも、朗文堂の和字シリーズのように、かな日本史とも呼べるような試みもある。
これらのかな書体との、「和漢混植」も多く使われている。この「和漢混植」によって、日本語の組版の見えは、全く変わってくる。こんなふうに。
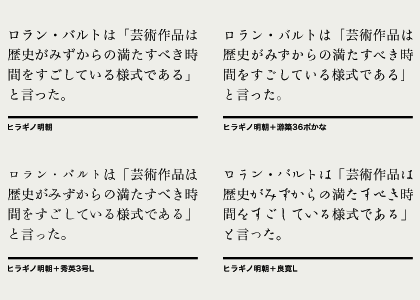
漢字はすべてヒラギノ明朝であるが、かな書体を変えるだけで、全く別の書体に見えなくもない。和文の、特に明朝体は、実はこんなにも表現の幅が広い。加えて和文組版の本質というのは、実はかな書体にあるのだとも言える。
漢字は言うまでもなく、かなに比べると画数が多い。複雑である。それゆえ、細かな変化が全体に見えにくい。かなは、シンプルな故、ちょっとした変化が全体に及ぼす影響が大きい。
もちろん、漢字書体にも微妙な差異による組版の見えの変化はある。それはまた別の話で書くことにして、日本が漢字から変化させて作り出した「仮名」は、1200年以上たった今でも、日本語表記、視覚的日本語の根底にあるのかもしれない。
投稿者 mikandesign : 02:48 AM | コメント (6) | トラックバック
May 16, 2005
lines 2
昨日の続きではないが、ちょっと別の角度から「線」を見てみたい。
今日本屋で
『眼の冒険−デザインの道具箱』 松田行正著 紀伊国屋書店
を購入。冒頭だけ読み進めると、早速第1章が「直線の夢」というタイトルから始まっていた。
その中で最も気になったフレーズ。
〈線は外界を模倣するのではなく、見えないものを見えるようにするのだ〉
メルロ=ポンティが、パウル・クレーの描く線について語った言葉らしい。見えているものをそのままなぞるのではなく、「見えるようにする」。
ここからは勝手な解釈だが、例えば激しい雨が降ることを表現するのに、直線を上から下に引く。そよ風を表現するために、緩やかなカーブの優しい線を引く。これらは眼に見えないものなのに、その空気を表現できる。これは誰しもがやっていることだし、漫画的表現と言われればそれまでだが、リアリティに対するひとつの「線の発明」と言えるだろう。もちろんクレーの描く線は、それ以上のものを生み出し、新しい視覚体験をつくった。要するに、単に認識の枠を超え、体験として屹立しているのだと思う。
それからこの『眼の冒険』の同じ章にはエティエンヌ=ジュール・マレーも登場するのだが、彼の実験したクロノフォトグラフィもやはり「線」である。「動き(運動)」を分析することが、ある「線」となり、そこに「時間」が見えてくる。

(前に、『人間人形時代』にあったマイブリッジのクロノフォトグラフィを使って、こんなGIFアニメも作ってみたことがあった。)

また、下のように
A
─────────
B
AとBの間に線を引くことで、AとBを分けることができる。これは、国境であったり、他者と自分であったり、こちらと向こうである。ここに「情報の単位」が発生する。
それは、クロノフォトグラフィに対して、「コマ」という単位を発生させ、シネマトグラフィへと発展していく過程でもあったのだと思う。
線を引く行為は簡単だ。だけど、それが何の線なのか、どういう意図があるのか、何を分け、何を生み出すのかを考えると、一本の線を引くことに、少しでもためらいを持つこともまた、必要かもしれない。
投稿者 mikandesign : 11:56 PM | コメント (8) | トラックバック
May 15, 2005
lines
昨日今日仕事している中で、ふと気になった「線」。
いわゆる「罫線」だ。(株式のチャートではない)
最初、活版印刷ではある程度決められた太さなり、種類であったと思う。
もちろん、フリーハンドの線が印刷できない訳ではなく、活字を組んで版面を作るという印刷の性格上、活字に罫線が含まれている方が効率が良く、美しい版面を設計できるのだろう。
例えばオモテケイ(細い罫線)、ウラケイ(太い罫線)という言葉は現在でも使われるが、もともと活字のボディの表側が細く、裏側が太くなっていて、これをひっくり返しながら使用していたことに由来する。
嘉瑞工房:活字について
他にも点ケイ、飾りケイ、子持ちケイ、など、活字の長い歴史の中で工夫がなされ、様々な需要に対応していったことは伺えるが、やはり印刷所のもっている活字の種類などによって、デザイン指定上の制約があったことは否めないだろう。
写植組版でも同様に、写植盤の種類によってある制約が生まれるのだろうが、
活版印刷とは違い、版下という印刷原稿をつくり、製版カメラで撮影できれば良いので、手描きで罫線を引く、ということができたはずである。
そうすると、フリーハンドであえて緩さをねらった罫線などももちろん可能となってくる。
ところが、当時のデザイナーは0.1mm以下の罫線を、ロットリングなどで引く訓練をしていたという話をよく耳にする。ようするに、機械的に正確でゆがみのない罫線が求められていたということである。これは活版印刷の影響そのままなのだろうか。
現在、DTPアプリケーションでは、ツールによってかなり簡単・正確に罫線を作成でき、また太さも自由自在にできる。そればかりではなく、フリーハンドの罫線も簡単に作成することができるように思える。しかし、デジタルならではの制約があり、[スキャン]→[画像調整・変換]→[貼込]と、版下作成に比べるとかなりの手間があることも事実である。
webではどうだろうか。
かつて、web上での罫線や、テキストベースでの罫線の種類を、テキストエディタ上でストックしていったことがあった。
ーーーーーーーーーー
==========
…………………………
−・ー・−・ー・ー・
など、単にテキストの種類、その組み合わせだけでも様々な罫線を作り出すことができるのである。これらはよく、ASCIアートやメールの署名などに使われている。
フリーハンドの線であれば、DTPの行程と同じようにして画像として配置することはある程度可能だ。そのようにしてデザインしたのが「少年文芸」という雑誌のプロモーションサイトである。
基本的に「罫線」は、直線的、硬質的なものの方が美しく、わかりやすいと思われているようだ。しかし、編集者Kさん曰く、丸ドットの罫線のように、図像に近いというか、そのように扱われるものもある。
要するに、「文字」「活字」としての罫線なのか、「図像」としての罫線なのかの境界が存在するのではないだろうか、という気づきだった。その二つがどう違うのかは、また後日考察。
投稿者 mikandesign : 03:40 PM | コメント (226) | トラックバック
May 10, 2005
about my work
仕事がたくさんある…。
フリーランスの僕にとっては非常にありがたいことだけど、
どうしてなかなか、時間と集中力のせめぎ合い。
生活=仕事、の生活。鶏と卵。
今日もひとつお話を頂いたが、昨今の事情により、お断りせざるを得なかった。
すみません。
自分で整理する意味を込めて、列挙。
今現在抱えてる仕事。
●websiteデザイン(というかデザインが終わっているので、ひたすらページ作成と修正。)
●機関誌(早く手をつけねば)
●ムック(もう次が始まる)
●雑誌のダイアグラム(早く案を練らねば)
●チラシ(今週末入稿か……)
●イベントの展示用パネル、その他ツール
など様々。うわー、結構あるな。
一番大変なのはメディアによって頭を切り替えなきゃならんこと。
パソコン上ではアプリを切り替えるという行為だけど、
どうやら脳のシステムとパソコンのシステムは違うらしく、簡単には行かない。フゥ
まあ、仕事があることに感謝して、がんばりどころ。
作るメディアによって、ある程度使うアプリは決まってくる。
例えば、webはDreamWeaver、チラシ・展示物はillustrator、ページ物はInDesignて言う具合に。
必ずしも、そのアプリで作る必要はないんだけど、道具だからなあ。
タバコに火をつけるときに、手元にライターがあるのに、ガステーブル使う人はいないだろうし。
ただ、このへんの道具の変化=プロセスの変化にも、なにかヒントはあるかもな。
そういえば、こないだデザインした書籍が出てた。
憲法千一夜
中山太郎著 中央公論新社

中山太郎という議員さんの本です。